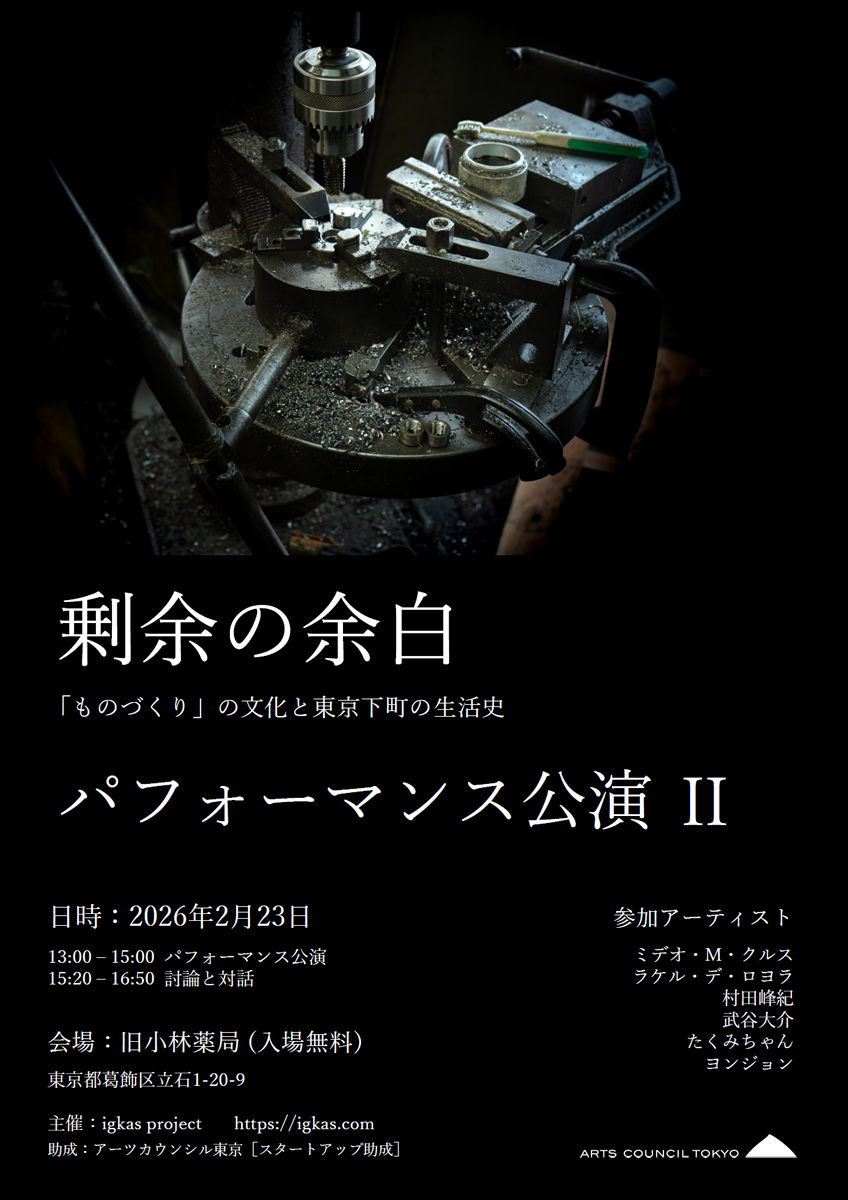千住で「ロボコン」決勝大会-各国から48人参加、「HANABI」テーマに腕競う

シアター1010(足立区千住3)で8月18日、「IDCロボットコンテスト大学国際交流大会」の決勝コンテストが開催された。主催は東京電機大学とIDC国際委員会。
1990年から始まり今年で20回目を迎える同大会は、4大ロボコン(高専ロボコン・大学ロボコン・ABUロボコン・IDCロボコン)の一つとしても知られる。今回は、東京電機大学が2012年に足立区に移転するのに伴い千住での開催が決まった。
今大会は、東京電機大学やマサチューセッツ工科大学など7カ国の大学から48人が参加。他のロボコンと異なり地域や大学の対抗でなく、参加者48人が4人12チームに分かれコンテストを競う。チーム分けされた12チームは10日間のロボットの製作期間の後、当日の予選リーグを経て上位8チームが決勝トーナメントに進む。
同大会は毎回テーマが決められているのも特徴。2000年のソウル大会は「南北経済協力」、2001年の大阪大会は「たこ焼き大回転」など開催地にちなんだテーマが設定される。今年は花火大会が行われる足立区にちなんで「HANABI」とし、花火の打ち上がる夜空と荒川をイメージしたフィールドが用意され、各チームが工夫したロボットの技術を競った。
中にはタイヤが外れるなどのハプニングがあったが、それぞれ工夫を凝らした仕組みで相手チームと接戦する場面も。予選で敗退したチームの日本人大学生は「悔しいけど後悔はない。とても楽しかった」と話し、国境を越えたチームメートとの交流を振り返った。
決勝戦では、予選リーグから勝ち上がったオレンジチームとレッドチームとの対決の対決となった。協議による再試合の末、レッドチームが優勝し、会場は大きな拍手に包まれた。
優勝チーム・オレンジチームの小島さんは「いい戦いができた。応援に感謝する」とコメント。同チームのメンバーも「チームメートの頑張りがあり、メンバーや人がとても良かった」と口々にし、10日間で生まれた国際交流の成果を語った。
審判を務めた東京電機大学の汐月哲夫教授は「ルールや設定は毎回違うが、今回は水と花火は特徴的な足立をイメージして作られた。今後もこのように地域に密着した世界的な大会ができれば」と話した。2012年に開校する同大に関しては、「地域とものづくりが交流できる街づくりの一翼を担えれば」とも。